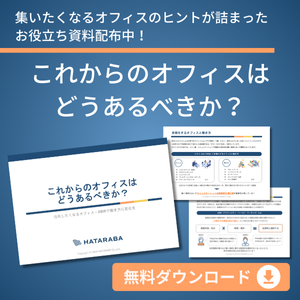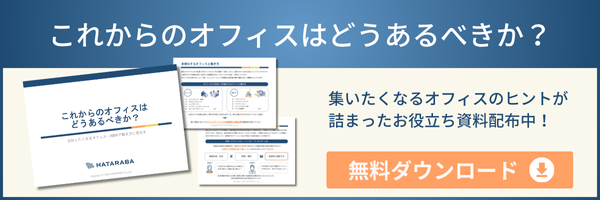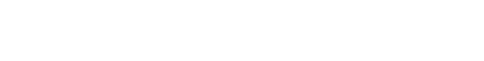近年、「地方移転」というキーワードが注目を集めています。テレワークの普及や働き方改革の進展を背景に、本社や主要拠点の一部を首都圏から地方都市に移す動きが活発化しており、単なるコスト削減策を超えた戦略的な選択肢として捉えられるようになっています。
本記事では、オフィスの地方移転に関する最新情報に加え、地方移転の理由や期待できる効果について解説していきます。
いま、なぜ地方移転?多様化する企業の拠点戦略
「地方移転」と聞くと、本社機能のすべてを地方都市へ移す大掛かりなものを想像するかもしれません。しかし、その形態は多様化が進んでおり、代表的な移転スタイルとして、以下のようなパターンがあげられます。
1.本社機能の完全移転:本社所在地を首都圏から地方都市へ完全に移転
2.地方拠点の開設:本社は残したまま、地方都市にサテライトオフィスや新たなオフィスを設け、働く人や機能を分散
3.特定部門の移転:R&Dやカスタマーサービス、バックオフィスなど、特定の部門だけを地方都市に移転
4.フルリモートワークの導入:物理点な移転は伴わないものの、地方や海外に移住する従業員が遠隔で業務を行うことで、実質的な地方分散を実現
これらの動きは、企業がオフィスを首都圏にのみ構えることで生じる人件費やオフィス賃料の高騰、災害リスクなどの課題に対する戦略的なソリューションとして注目されています。さらには、地方移転により、イノベーションの創出や地域社会との共生といった新たな価値創造を図る動きも見られ、多くの企業が「どこにオフィスを構えるか」を再考し、組織体制や拠点戦略を再構築するフェーズを迎えています。
地方移転が加速中!データで読み解く本社移転のリアル

日本における本社移転の動向は、長らく「転入超過」が続いていた首都圏から、近年新たな変化の兆しを見せています。特に2020年を機に、首都圏からの転出の流れは大きく加速していきました。
帝国データバンクの調査によると、2024年に首都圏から地方都市へ本社を移転(転出)した企業は年間で363社に上り、1990年以降最多を更新しています。年間の転出企業数が300社を超える状況は、2021年より4年連続で続いており、地方移転トレンドが継続していることを示しています。
地方都市へ転出した企業規模を見てみると、売上高が1億円未満の企業数が176社と最も多くなっています。これは、IT関連スタートアップを中心とした小規模企業による、コロナ禍以前からの地方移転トレンドが牽引している動きと言えるでしょう。2022年以降には、売上高10〜100億円未満の中堅規模の企業も、この地方移転の流れに加わるようになったことで、首都圏から地方都市へのオフィス移転はさらに活況を呈するようになりました。
コロナ禍当初は、経営環境の悪化に伴うコスト負担の増大に対する解決策として、地方移転を選ぶ企業が急増したものの、2023・2024年になると、地方移転後も業績が増収となる企業が増加傾向に転じています。このことから、地方移転が単なるコスト削減のための選択肢ではなく、成長戦略のための選択肢のひとつとして進化を遂げていることが伺えます。
出典元: 帝国データバンク「全国企業『本社移転』動向調査(2024年)」
コロナ禍以降も衰えない。企業が地方移転を選ぶ4つの理由

企業が地方移転を選択する背景には、未来を見据えた戦略的な狙いがあります。ここからは、代表的な4つの理由を紹介していきます。
理由1:コストの最適化
企業の地方移転がもたらす最も直接的なメリットの一つは、コストの最適化です。地方都市のオフィス賃料は、首都圏と比較して格段に低い傾向にあり、本社機能の移転や大規模な拠点開設であれば、年間数千万円から億単位の削減効果も期待できます。
また、地域によっては人件費の水準が異なるため、賃金だけでなく交通費や通勤手当といった諸経費の抑制にも繋がる可能性があります。さらに、地方都市では採用競争が比較的緩やかであることから、採用活動にかかるコストを抑えられる場合もあります。
これらのコスト削減効果は、企業の収益性を高めるだけでなく、新たな事業投資や研究開発への原資を生み出すことにつながります。
理由2:多様な人材の確保と定着
Uターン・Iターンや人材や、地元での活躍を志す優秀な人材は、事業成長を加速させる貴重な戦力です。都市部での経験を持つ人材が新たなイノベーションをもたらし、地元を深く理解する人材は、地域に根差した持続的な事業展開の核となります。 この両者を獲得することは、企業の競争力を大きく高めるでしょう。
また、通勤ストレスの少ない地方都市での勤務は、従業員のワークライフバランスを向上させ、結果的に健康増進につながります。これにより従業員の満足度が高まり、離職率の低下やエンゲージメントの向上にも寄与するため、長期的な視点での人材定着を見込むことができます。
理由3:BCP強化
東日本大震災以降、企業にとってBCP(事業継続計画)対策の重要性は、かつてないほど高まっています。特に首都圏への一極集中は、大規模災害が発生した際に事業全体が停止してしまうリスクを増大させる要因となります。
このようなリスクを効果的に分散させる手段としても、オフィスの地方移転は注目されています。本社機能や主要拠点を複数箇所に分散させることで、たとえ特定の地域で災害が発生しても事業全体が停止する可能性を大幅に低減できます。さらに、災害時の電力供給や通信環境を確保することで、自然災害にとどまらない不測の事態に対しても揺るがない、強固な事業基盤を築くことが可能です。
理由4:地域社会との新たな価値創造
地方移転により、地域社会との関わりを深めることは、地方創生に寄与し企業のCSR活動強化につながります。地方自治体との連携による雇用創出や地域経済の活性化はもちろん、その地域特有の資源や文化・技術をもとに、画期的な製品やサービス、事業モデルが生まれる可能性も秘めています。
また、近年は企業誘致に積極的に取り組む地方自治体も増えていることから、補助金や税制優遇、土地の提供や人材確保支援などの手厚い特典を受けることができます。移転にかかる初期費用や拠点運用コストの軽減は、新たな土地での挑戦や成長を力強く後押ししてくれるでしょう。
地方移転の光と影。企業にもたらす効果と乗り越えるべき壁
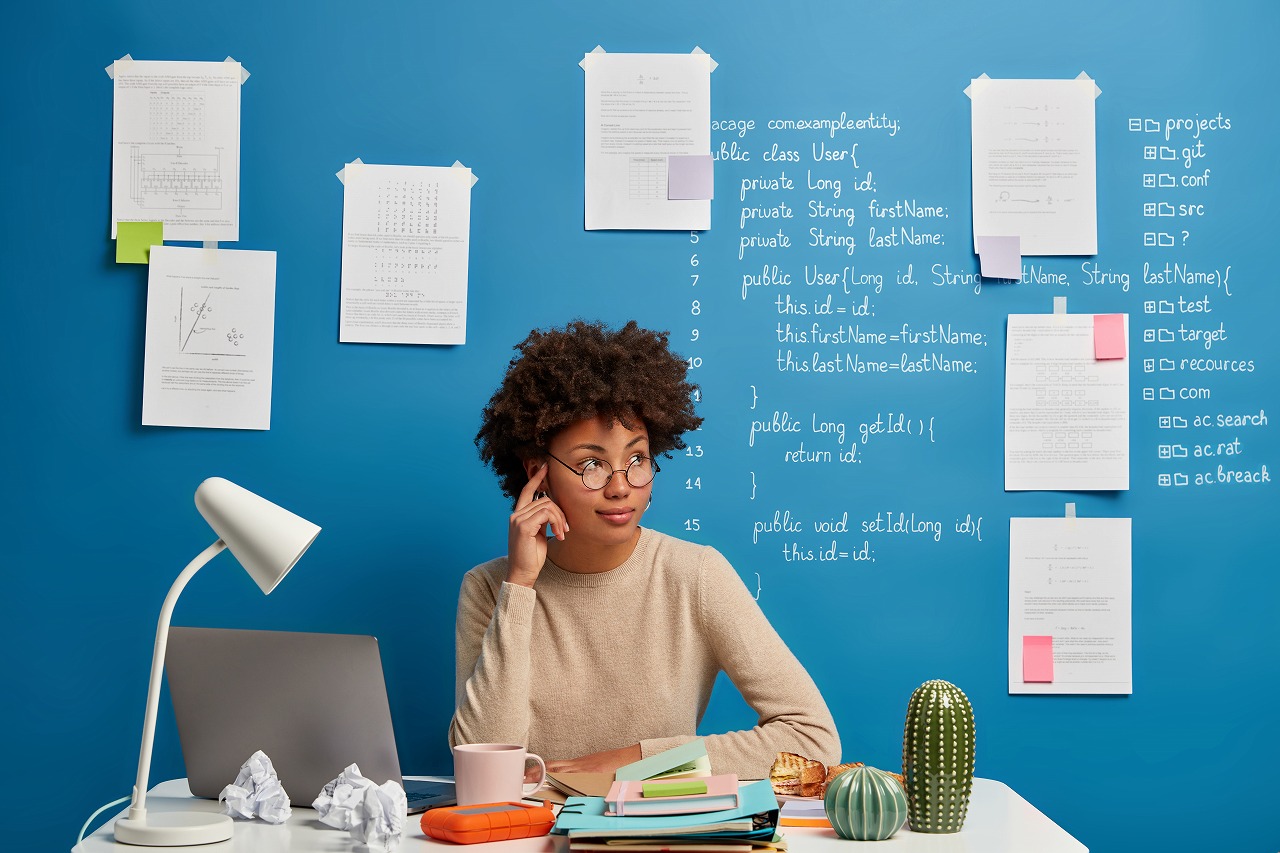
地方移転は、企業に多様なメリットをもたらす一方、乗り越えるべき課題も存在します。地方移転を成功させるためには、メリットとリスクの両面を理解し、戦略的に対応することが大切です。
地方移転がもたらす主なメリット
・従業員のワークライフバランス向上と心身の健康
首都圏の通勤ストレスなどから解放されることで、従業員の満足度と生産性の向上が期待できます。
・多様な人材確保と、新たな視点によるイノベーション創出
Uターン・Iターン人材や地域に根差した人材など、新たな人材プールにアクセスでき組織の活性化に繋がります。
・地域貢献活動を通じた企業ブランド価値の向上
地域社会の一員として貢献する姿勢が、企業の社会的評価やブランドイメージを高めます。
乗り越えるべき主なリスクと課題
一方で、以下のようなリスクと課題には周到な対策が求められます。
・人材の確保と定着の困難
移転に伴う既存社員の離職や、地方都市における専門人材の採用が難航してしまうリスクもあります。
・取引先・顧客との関係希薄化や、拠点間における連携不足
首都圏の主要な取引先との物理的な距離が生まれ、対面でのコミュニケーション機会が減少する可能性があります。また、拠点間の情報格差や心理的な壁が生まれやすくなります。
・移転先のインフラ環境の整備
移転費用だけでなく、業務プロセスの再構築や事業インフラの整備に、予期せぬコストや時間がかかるリスクがあります。
成功に向けた綿密な計画の重要性
企業にとって成長戦略の一つでもある地方移転は、周到な準備と関係各所への丁寧な対応によって、大きなリターンが期待できる選択肢です。移転後に様々なリスクが露呈してしまわないように、多角的に仮説・検証を繰り返しながら、綿密な計画を策定したうえで臨むようにしましょう。
地方移転は未来への投資!企業と地域が共に描くサステナブルな成長戦略

コストの最適化・多様な人材の確保・BCP強化、そして地域との連携による新たなビジネスの創出など、企業の成長戦略に欠かせない様々な課題の解決に対し、オフィスの地方移転は効果的な起爆剤となり得ます。また、企業の競争力・経営基盤の強化だけでなく、移転を通じて、企業が日本の地方創生や持続可能な社会実現に対し、どのように寄与していくかという点にも多くの注目が集まっています。
オフィスの地方移転が進むことで、それぞれの地域社会にとって、企業が共に未来へと歩む重要なパートナーとしての役割も担うようになり、その結果、より強固なレジリエンスと高い社会貢献価値をバランスよく確立する企業が増えていくのではないでしょうか。