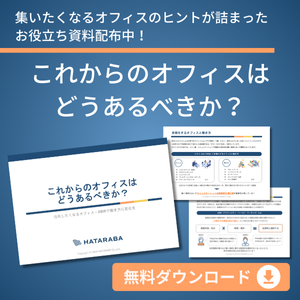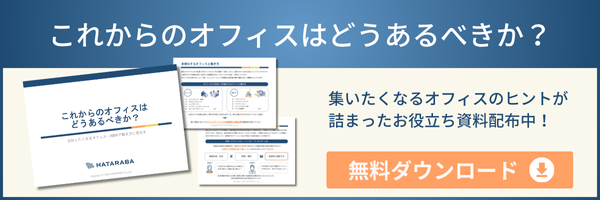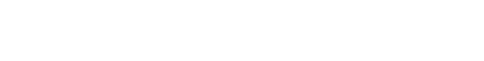働き方の多様化が進む中、企業にとってオフィス戦略は重要な経営課題となっています。特に、オフィス機能を集約するか分散するかという選択は、企業の生産性や従業員の働き方に大きな影響を与えます。
本記事では、オフィス機能の集約と分散双方の選択におけるメリット・デメリットをふまえながら、今後のオフィス戦略について考察していきます。
オフィスの集約・分散とは?
近年、テクノロジーの進化や社会情勢の変化に伴い、「オフィス」という場所のあり方は多様化が進んでいます。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を取り入れる企業が増える中、注目されているのが、オフィス機能の「集約」と「分散」という選択肢です。
「集約型オフィス」が、企業の主要部門や各部門の従業員が一つの拠点に集まって働くオフィススタイルであるのに対し、「分散型オフィス」は、本社機能の一部を地方に移転したり、サテライトオフィスを複数設置したりするなど、オフィス機能を地理的に分散させるスタイルを指します。
コロナ禍でのリモートワークの浸透により「分散型オフィス」が注目された一方で、収束後には対面コミュニケーションの価値が再認識されたことで、業務効率向上を重視する企業の間では「集約型オフィス」へと舵を切る動きが目立つようになっています。
集約型オフィスのメリット・デメリット

ここからは、集約型オフィスのメリット・デメリットについて解説していきます。
集約型オフィスのメリット
集約型オフィスでは、以下のようなメリットが生まれることが考えられます。
コミュニケーションの活性化
企業文化の浸透
セキュリティの強化
コスト効率の向上
従業員が同じ場所に集まって働くことで、業務上の報連相がスムーズになるだけでなく、日常のちょっとした雑談やアイデアを共有する機会も増えることから、社内のチームワークや連帯感が向上します。また、上司や他部署の従業員、経営層とも直接顔を合わせる機会が増えることで、企業理念や価値観、文化が社内全体に浸透しやすくなり一体感が生まれます。
さらに、働く人が集約されることで意思決定の透明性・公正性の確保や情報漏洩リスクに対する対策が講じやすくなるため、ガバナンスと情報セキュリティ双方において体制を強化できるでしょう。
加えて、会議室や休憩室などのスペースや設備、各種備品を多くの人で共有することで、コスト効率を高める効果も期待できます。
集約型オフィスのデメリット
一方で、集約型オフィスには以下のようなデメリットも考えられます。
集約にかかるコスト発生
固定費の増加
通勤負担の増大
オフィス機能の集約は、従業員はもちろんさまざまな設備や家具の移動や整理が必要となる一大プロジェクトです。各部署との調整や物品の調達など事前準備は多岐にわたります。集約後も業務が円滑に遂行するまでの間、さまざまな調整や改善策を講じる必要があるため、多大なリソースが割かれることになります。また、集約によりオフィスの移転やフロア拡張、設備増強などを行ったことで、賃料や光熱費などの固定費が高額になる可能性もあります。
加えて、オフィスへの通勤に伴い、従業員には時間的・精神的負担がかかることも考えられます。特に都市部での通勤ラッシュによるストレスは、従業員のモチベーションにもマイナスな影響をもたらしかねません。リモートワークによる柔軟な働き方を希望していた従業員にとっては、毎日のオフィス出社・定時勤務は難しいと感じることもあるため、企業側は従業員のワークライフバランスに配慮した対策を講じることが求められるでしょう。
分散型オフィスのメリット・デメリット

次に、分散型オフィスのメリットとデメリットをみていきましょう。
分散型オフィスのメリット
分散型オフィスでは、以下のようなメリットがあげられます。
ワークライフバランスの向上
優秀な人材の確保
固定費の削減
BCP対策の強化
サテライトオフィスや自宅からのリモートワークを積極的に取り入れることで、従業員にかかる通勤負担が軽減されることから、時間的・精神的に余裕をもって仕事に取り組みやすくなります。分散型オフィスは、フレックスタイムをはじめとする柔軟な働き方との親和性が高いため、趣味や育児・介護などのプライベートな時間と仕事を両立しやすくなります。
加えて、地方拠点やフルリモートでの就業など勤務地の選択肢が広がることで、これまでの地理的な障壁がなくなり、地方や海外に暮らす優秀な人材を採用できる機会が広がります。場所や時間を問わず自分のライフスタイルに合わせて働ける環境は、従業員のやる気や満足度向上につながるため、企業イメージアップや人材獲得においてもポジティブな影響が生まれると考えられます。
固定費の観点からも、都心部と比較して賃料や維持費が安い地方都市に拠点を移すことで負担軽減につながることが期待できます。さらに、地方にオフィス機能を分散させることで、本社で災害などの非常事態が発生したとしても他の拠点で業務を継続できることができるため、BCP対策としても高い効果が期待できます。
分散型オフィスのデメリット
分散型オフィスのデメリットには、以下のようなものがあげられます。
コミュニケーションギャップの拡大
マネジメント難易度の上昇
コスト負担の増大
従業員がいろいろな場所で働き、互いの物理的な距離感が広がることで、日常会話やちょっとした相談などのカジュアルなコミュニケーションの機会が減少していきます。コミュニケーション機会の減少は、チームの連携強化や企業文化の醸成を妨げるだけでなく、従業員個人のモチベーション低下にもつながります。さらに、互いの働きぶりが見えにくくなることで、業務進行や労務などのマネジメントが適切に行えなくなるケースも考えられます。
また、サテライトオフィスを開設するなど拠点を分散させると、それぞれのオフィスで設備や備品にかかるコストが発生します。拠点数や設備内容・利用者数などによっては、初期費用と維持管理費の双方でコストが大きく膨らむ可能性があります。
オフィス戦略の未来

新型コロナウイルスの感染拡大という一つのきっかけで、広く浸透していった分散型オフィス。このように、オフィスのあり方はその時々の社会情勢や事業環境によってさまざまな影響を受けます。では、これからの未来を見据えた時、企業はどのようなオフィス戦略を講じることが求められるのでしょうか。
意識すべき点として「柔軟性」「テクノロジー」「従業員体験」の3点があげられます。
多様な働き方へのニーズに応え、リモートワークやフレックスタイムに対応した柔軟な環境が、従業員のワークライフバランスの実現とパフォーマンス向上につながるオフィスのあり方として定着していくでしょう。そして、時間や場所にとらわれず高いパフォーマンスを発揮するためには、安定した通信環境や業務の透明性を保つシステム導入など、最新テクノロジーの活用が不可欠です。利便性・機能性・柔軟性を兼ね備えた環境設計により、オフィスが従業員一人ひとりにとって生産性高く快適に働くことができ、充実感を得られる場所となることが今後のオフィス戦略の目指す姿となるのではないでしょうか。
集約と分散の良いとこどりで、自社に最適なオフィス戦略を目指そう!

働き方の多様化が進む現代、自社に最適なオフィスのあり方は、集約と分散の二者択一で決められるものではありません。コミュニケーションの活性化や企業文化の醸成が期待できる集約型と、固定費の削減やワークライフバランスの実現に貢献する分散型。それぞれの利点を活かしながら、企業の目標や従業員のニーズに合わせて組み合わせるハイブリッドワークは、多くの企業にとって自社にとっての最適解を見出す鍵となります。
自社の抱える課題の解決や、さらなる成長を目指すなら、豊富な実績と知見を持つオフィス戦略のプロに一度相談してみることで、オフィスのさらなるブラッシュアップが期待できるでしょう。